「おがくず」って、聞いたことありますか?
木を切ったり、削ったりしたときに出る、ふわふわの細かい木くずのことです。漢字では「鋸屑(おがくず)」と書きます。「木の粉みたいなもの?」と思ってもらえたら、近いイメージかもしれません。
木の香りがふわっと広がる、とても自然な素材です。
昔から、暮らしのそばに
おがくずは、昔の日本の暮らしにとって、とても身近で頼りになる存在でした。
たとえば、かまどで火をおこすとき。新聞紙の代わりにおがくずを使うと、よく燃えて火がつきやすかったそうです。薪のあいだに詰めることで、火を長持ちさせる工夫もされていました。
また、土間や床下、昔の簡易トイレに敷いて、においや湿気をおさえるためにも使われていました。今のような消臭剤や除湿グッズがなかった時代、自然の力を借りて、清潔な暮らしを守っていたのです。
冬の寒い時期には、「おがくずこたつ」というものもありました。木箱の中に火鉢を入れ、そのまわりにおがくずをたっぷり詰めて、上に布団をかけて使う。ほんのりあたたかく、やさしいぬくもりがあったそうです。
生ゴミや魚などのにおいが気になるものを包んだり、お漬物を干すときに水分を吸わせたり。特に「たくあん」を干すときに、おがくずをまぶして縁側に並べる風景は、昔ながらの田舎の暮らしを思い出させます。
おがくずは、「包む」「守る」「抑える」など、日々のちょっとした困りごとをそっと助けてくれる、そんな存在でした。捨てるなんてもったいない。自然とともに生きていた時代、おがくずにはちゃんと居場所があったのです。
今の暮らしでも
現代でも、おがくずは活躍しています。
ペットのトイレ砂や、園芸用の「マルチング材」として使われたり、草の乾燥や土の温度調整、見た目のアクセントにもなります。
さらに、ひのきなど香りの良い木のおがくずは、消臭グッズやリラックス用の香り袋としても人気です。自然素材なので、使い方はアイデア次第。ちょっと暮らしをやさしくしたいとき、そっと取り入れたくなる存在です。
ふわっと、やさしい
おがくずは、木を加工する過程で生まれる“端っこ”からできています。一見、いらないものに見えるけれど、そこにはたくさんの知恵や、やさしさが詰まっています。
ふわふわで軽くて、手に取るとどこかほっとする。そんなおがくずの魅力を、私はこれからも大切に伝えていきたいと思っています。
このブログ「おがくず日和」では、おがくずにまつわる小さな物語や、暮らしの中でのアイデアを、少しずつ綴っていきます。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
「おがくずってなぁに?」という小さな疑問が、
すこしでもやさしく、あたたかく届いていたら嬉しいです。

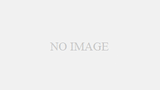
コメント